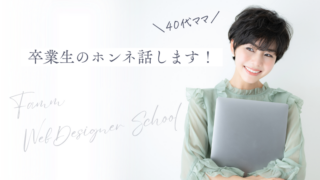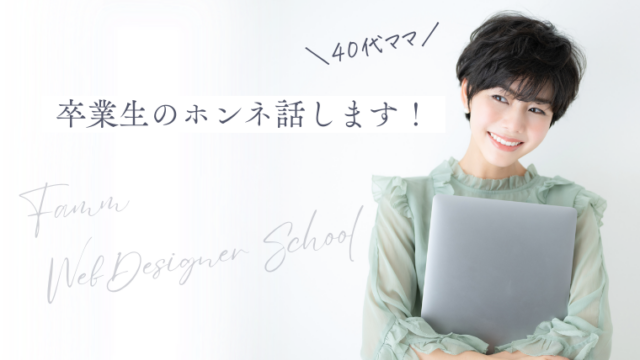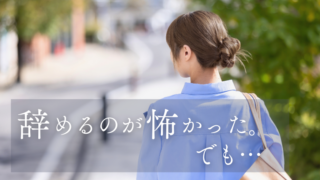息子の「小1の壁」をきっかけに正社員を辞め、在宅ワークでwebデザイナーをしているchieです♩
Webデザインの学び方に迷っていませんか?
webデザインの勉強をはじめてみたけど──
- このまま独学で進めていいの?
- スクールって本当に必要?
- 将来、仕事にするにはどう学ぶべき?
そんなふうに、「学び方」そのものに迷い始めていませんか?
私も、まったく同じ道を通ってきました。
YouTubeで学習したりCanvaを触り始めてみて、「楽しいけど、このままでいいのかな」と不安になったこと、何度もあります。
でも、遠回りしたからこそ気づいたんです。
Webデザインを仕事にしたいなら
実は「何を学ぶか」よりも「どう学ぶか」がすごく大事。
◆ 独学・スクール・ツールの違いと選び方
◆ 学び方がわからず失敗したリアルな体験談
◆ 私が遠回りしてたどり着いた「仕事につながる3ステップ」
Webデザインの学び方に迷うあなたにヒントになればうれしいです。
Webデザインの仕事につながる3ステップ(全体像)

まず最初に──
これが、私がたどり着いたWebデザインが仕事につながる”3つのステップ”です。
STEP1|まずは“見た目を整える”デザインの基本を学ぶ
STEP2|“サイトをつくる”ことで、伝わる流れを覚える
STEP3|「売る仕組み」を考えるマーケティングの力を知る
この全体像を最初に知っておくことが、最大の近道でした。
やみくもに手を動かすのではなく、
「自分は今、どこにいるのか」「何が足りていないのか」が明確になることで、必要なスキルを効率よく身につけられるようになったんです。
このあとの章では、それぞれのステップをより詳しく解説しながら、
「どんな学び方が自分に合っているのか?」を判断するヒントをお伝えしていきますね。
Webデザイン初心者がよく迷う「独学・ツール・スクール」の基本まとめ

Webデザインを学びたい!と思ったときに、
まずぶつかるのが「どうやって学ぶのが正解かわからない」という壁ではないでしょうか。
-
独学って、本当にできるの?
-
どんなツールを使えばいいの?
-
スクールって高そうだけど、必要なのかな?
私も、まさにそうでした。
検索すれば、無料で学べるサイトも出てくるし、CanvaやPhotoshopなどのデザインツールもいろいろ。
でも、何をどこまでやればよくて、どこから有料スクールに行くべきなのか──
正直、誰かに相談したくなるくらい迷っていました。
そして私は40代という年齢もあって、「この時間と労力、本当にムダにしたくない」と強く思っていたんです。
ここでは、そんな「最初のつまずきポイント」を整理するために、私自身が学び始めた頃の経験を交えながら、わかりやすくお伝えしていきますね。
独学はできるけど、挫折しやすい理由
今は、Webデザインを独学で学べる環境が本当にたくさんありますよね。
ProgateやYouTube、Canvaなど、無料から始められるツールも多く、私も最初は「まずはお金をかけずにできないかな」と思って少しツールを触っていました。
ゲーム感覚でプログラミングを学んでみたり、動画を真似しながらバナーを作ってみたり。
Canvaでそれっぽいデザインができたときは、「私にもできるかも!」と嬉しくなったのを覚えています。
最初はそれなりに楽しかったし、「私にもできるかも!」と思っていたんです。
でも、だんだんとこんな不安が出てきました。
-
これって、どこまでできれば“仕事”になるの?
-
この学び方で、本当に合ってる?
-
次は何をすればいいんだろう…
教材をひと通り終えても、「結局、自分に何ができるようになったのか」がわからず、
できるようになっている実感が持てない。
そしてそのまま不安になって、手が止まってしまう。
──これが、私が直面した独学の落とし穴でした。
しかも私の場合、Webデザインを学び始めたのは40歳を過ぎてから。
若い頃のように「とりあえずやってみる!」という勢いだけでは動けなくて、
「本当にこの学び方で合ってるのかな?」と、何度も立ち止まりました。
決して独学が悪いわけじゃない。
でも、学ぶ順番やゴールを自分で設定できないと、すごく挫折しやすい。
今なら、そうはっきり言えます。
▼ 独学でできるWebデザイン学習サイトまとめました
| サイト名 | 学べる内容(やさしい表現) | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|---|
| Progate | HTML・CSSの基本や簡単なプログラミング | スライド形式。初心者に優しい | 無料プランあり |
| ドットインストール | Webページ作成の基礎とプログラミング入門 | 3分動画で学べる | 一部無料・プレミアムあり |
| chot.design | Webデザインの基礎・画像加工・簡単なサイト制作 | 実践向け・掲示板付き | 無料 |
| SkillHub | バナー制作・ホームページ制作の基礎 | フリーランス向け動画講座 | 無料 |
| Udemy | 画像編集やWebデザインの操作を動画で学べる | 買い切り型。講座種類豊富 | 有料(セールあり) |
初心者が最初に使うべきツールはどれ?
まずは「作ってみる」から。Canvaで“できた!”を体験しよう
Webデザインを学び始めて、最初にぶつかるのが「どのツールを使えばいいの?」という疑問。
まず最初に知っておいてほしいのが、Webデザインには大きく分けて2つのスキル領域があることです。
- デザインスキル(見た目・レイアウトなど)
- コーディングスキル(HTMLやCSSなどで形にする力)
もちろん、両方できた方が強みになりますが、最初から全部を一気に学ぶ必要はありません。
「ちょっと面白そう」「何か作ってみたい」という気持ちがあるなら、まずはCanvaを触ってみるのがおすすめです。
Canvaのいいところ
-
無料で使える
-
スマホアプリでもOK
-
テンプレートが豊富で操作もシンプル
-
とりあえずそれっぽいものが作れる
-
「私でもできた!」という成功体験が得られる
私も最初は、Canvaでバナーを作って「デザインって楽しい!」とワクワクしたのを覚えています。楽しくないと学びを進められないですよね!
Canva“だけ”では広がらない。その先に必要な本格ツールとは?
もちろん、Canvaだけでも仕事になるケースはあります。
たとえば👇
-
Instagramの投稿画像
-
ブログのアイキャッチ
-
単発のバナー制作 など
でも、単価は数百〜数千円程度で、納品して終わりということが多く、
「継続的に受注する」「提案もできる」デザイナーになるには難しいのが現状です。
もしあなたが──
-
クライアントの要望に合わせてゼロから構成を考えたい
-
LPやWebサイトをちゃんと作れるようになりたい
-
「言われたことを形にする」だけでなく提案もしたい
…そう思っているなら、PhotoshopやFigma、Illustratorといった本格的なデザインツールにステップアップするのが必要です。
▼ Webデザインツールまとめ
| ツール名 | 向いている人 | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|---|
| Canva | とにかくまず作ってみたい人 | 無料・テンプレ豊富・操作が直感的でやさしい | 無料(一部有料プランあり) |
| Photoshop | 画像編集・バナー制作を極めたい人 | 写真加工や合成に強く、デザイン業界の定番 | 有料(サブスク制) |
| Figma | Webサイト・アプリ設計に興味がある人 | UI/UX設計に強く、共同編集もできる | 無料プランあり(有料プランあり) |
| Illustrator | ロゴ・アイコン・印刷物を作りたい人 | ベクター形式で高精度な図形制作が可能 | 有料(サブスク制) |
独学とスクール、どっちが合う?迷ったときの判断ポイント
Webデザインの学び方でよく出てくるのが、「独学でいける?それともスクールに通うべき?」という悩みですよね。
私自身も、最初はこの選択にすごく迷いました。
調べてみると、スクールにはそれなりの費用がかかるし、独学ならコストはかからないけど、ちゃんと続けられるか不安で…。
どちらが正解ということはありませんが、自分の性格や環境に合った方法を選ぶことが何より大切です。
▼ 独学とスクールの違いを比較してみました
| 比較ポイント | 独学 | スクール |
|---|---|---|
| 費用 | ◎ 安い(無料〜) | △ 数万円〜数十万円 |
| 学習ペース | ◎ 自由に進められる | △ カリキュラムに沿って進む |
| 質問・サポート | △ 自分で調べる必要あり | ◎ メンター・質問対応あり |
| モチベーション維持 | △ 自力で継続が必要 | ◎ 環境と仲間で支えられる |
| 向いている人 | 自分で調べるのが得意/継続できる人 | 不安が強い/最短で仕事につなげたい人 |
私自身は、「モチベーションの維持に不安があった」のと、「最初に順番を整理して学んでおきたい」という気持ちから、独学ではなくスクールを選びました。
とはいえ、家計のこともあり、大きな出費は避けたくて…
結果、短期&低コストで学べる1ヶ月完結「Fammママwebデザイナースクール」を選びました。

遠回りして気づいた私の体験談|「それっぽく作れたけど、まったく伝わらなかった」

FammスクールでWebデザインの基礎を学び終えたあと、「このスキルを、どうやって仕事につなげよう?」と模索していた時期がありました。
そんなときに耳にしたのが👇
「LP(ランディングページ)は、1枚で完結するから納品が早くて効率的」
「単価も高めだから、フリーランスにぴったり」
この言葉にすごく惹かれて、「LPなら私にもできそう」「仕事にしやすいかも」と思うようになったんです。
それからは、構成テンプレを調べて見よう見まねでLPを組み立てて、バナーやボタンもそれっぽく作り、とりあえず1本、形にしてみました。
ちょうど知人が個人でサービスを始めるタイミングだったので、「試しにLPを作らせてほしい」とお願いし、実際に公開までこぎつけました。
「それっぽいページができた!」「これが案件につながる第一歩かも」と思っていました。
でも──
LPとしての成果は、まったく出ませんでした。
「何が悪かったのか?」が自分でもわからず、「やっぱりセンスがないのかな」と落ち込んだのを覚えています。
気づきを与えてくれたのは、次に関わった実案件でした。
その後、別のLP案件に携わる機会をいただきました。
そこでは、ディレクターさんが構成・設計をすべて用意してくれていて、私はその内容に沿って、デザインを担当するという役割でした。
そのときに、ようやくはっきりわかったんです。
「LPって、“設計がすべて”だったんだ」と。
この気づきは、LPに限らずホームページやバナーにも当てはまりました。
「おしゃれ」「見やすい」といった表面的な要素だけでは、
相手に届くものにはならないということ。
正直なところ、こうした設計についての視点は、私が通ったスクールではほとんど教わることはありませんでした。
たとえLP特化型のスクールや講座に進んでいたとしても、もし構成や設計が学べない内容だったら──
そこに気が付かずやっぱり同じように、遠回りしていたと思います。
実はLPを作れるだけでは、仕事にはならない

「LP(ランディングページ)は、1枚完結で納品も早い」
「単価も高めで、初心者でも収入につながりやすい」
Webデザインを学び始めると、そんな言葉を目にし「LPを学べば稼げるかも」と感じる方も多いのではないでしょうか。
──私もそのひとりでした。
(※その話は前章で書いたので、ここでは割愛します)
この章では、これからLPを学ぼうと思っている方が遠回りしないように、
LPとは何か?どんなスキルが必要なのか?
そして、なぜ「作れるだけ」では意味がないのかをわかりやすくお伝えします。
LP(ランディングページ)とは、「売るための1枚ページ」
LP(ランディングページ)は、特定の商品やサービスを紹介し、
読者に「申し込み」「購入」などのアクションを起こしてもらう1ページ完結型のWebページです。
ホームページのようにメニューや複数のページがあるのではなく、
スクロールだけで完結し、1つの「行動」に特化した構成になっています。
SNS広告やキャンペーンなどからリンクされることも多く、まさに成果(売上)に直結するページです。
成果を出すには、“見た目のデザイン”よりも「設計」が大事
LPで結果を出すには、デザインスキルだけでは足りません。
必要なのは、“読み手の行動をゴールまで導くための設計力”です。
たとえば👇
-
誰に向けたページなのか?(ペルソナ設計)
-
どんな悩みを持った人が読むのか?(共感設計)
-
どの順番で情報を伝えれば行動してもらえるか?(構成設計)
こうした流れを設計できなければ、いくらおしゃれに見えても、ただの「流し読みされるだけのページ」になってしまいます。
この設計力こそが「マーケティング視点」
-
ページ全体の構成
-
情報をどの順番で配置するか
-
読者の感情をどう動かすか
-
最後にどんなアクションへ導くか
こうした設計はすべて、マーケティングの視点がなければできません。
つまり、LPを作る=マーケティングを設計することなんです。
「伝わらないLP」を生む、ありがちな誤解
LPはシンプルで短期間で仕上がる──
そんなイメージから、初心者でも取り組みやすいと思われがちです。
私もそう思っていました。
たとえば、テンプレートを使って👇
- ヘッダーを入れて
- 実績を入れて
-
ボタンを置いて
一見、それっぽく並べれば完成するように見えます。
でも、なぜその順番で?なぜその言葉で?がわからなければ、どれだけ整っていても、読者は行動してくれません。
私は実際に「見た目はキレイ。でも反応ゼロ」のLPを作ってしまい、「なんでだろう」と頭を抱えたことがあります。
今ならはっきりわかります。
伝わらないのは、デザインじゃなく「設計」がないからだった。
LPは「マーケティング視点で設計する」もの。
ここまで読んで、「LPってむずかしいんだ」と思った方もいるかもしれません。
でも、これは不安ではなくチャンスです。
なぜなら、この設計力こそが、他のデザイナーと差がつく部分だから。
このあとの章では、そんな気づきをもとに「Webデザインをどう学んでいけばいいのか?」を、3つのステップに分けてわかりやすく解説していきます。

Webデザイン仕事につながる学び方|遠回りしたからこそ伝えたい3ステップ

この章では、Webデザインを仕事につなげたい人のために、 私自身が実際に遠回りしたからこそ見えてきた「3つのステップ」を深掘りしてご紹介します。
40代から学び直した私だからこそ、 まず全体像を最初に知った上で、自分に合う学び方を取捨選択することが、何よりも近道になると実感しています。
STEP1|まずは“見た目を整える”デザインの基本を学ぶ
最初に身につけたいのは、「見た目を整える力」です。
-
配色や文字のバランス
-
レイアウトの基本ルール
-
見やすく・伝わりやすい情報配置のコツ
この段階では、とにかく手を動かして「作ってみる」ことが何より大切です。
CanvaやFigmaなどのツールを使って、SNSバナーや画像を真似て作ってみるところから始めてOK。
- Canvaのテンプレートをいじって遊んでみる
- バナー模写から「なんとなく配置バランス」を掴む
- デザイン4原則(近接・整列・反復・コントラスト)を意識するだけで見栄えが激変
- PhotoshopやFigmaの操作だけでなく、「なぜこうデザインするか」が学べるカリキュラムを選ぶ
- 質問できる環境があると、つまずきポイントも解消しやすい
STEP2|“サイトをつくる”ことで、伝わる流れを覚える
次は、Webサイトの制作を通して「使いやすく伝わる流れ」を作る力を学びます。
-
トップページと下層ページの構成
-
メニューやボタンなどの導線設計
-
WordPressやSTUDIOを使った実践的なサイト制作
このステップでは、「誰に、どの順番で何を伝えるか」の相手目線を意識する練習になります。
- ProgateやドットインストールでHTML/CSSを学ぶ
- 導線や情報の並びを紙に書き出してワイヤーを作ってみる
- 直感的に操作できるSTUDIOを使って自分のポートフォリオを作ってみるのもおすすめ
- ホームページ制作が含まれているか確認
-
構成・導線・ワイヤーフレームなどが学べる講座だとLP制作にもつながる
STEP3|「売る仕組み」を考えるマーケティングの力を知る
最後に身につけたいのが、「成果につなげるための設計力」。
LPなどの実案件で求められるのは、この視点です。
学ぶべきことは👇
- 誰に向けた内容か?(ペルソナ)
- どんな順番で読ませるか?(構成設計)
- どんな感情を動かすか?(コピーや導線)
- 最後にどんな行動をとってもらうか?(CTA設計)
この設計力こそが、「仕事として成果を出せるデザイナー」になるための土台になります。
- 成果の出ているLPを見て「なぜこの順番か?」を分析する癖をつける
- 書籍やSNSでも“構成解説”されているものを参考にする
- コピーライティングや行動心理も少しずつ学んでおくと◎
- LP特化型でも「構成設計」や「マーケ思考」が含まれているかは必ずチェック
- ペルソナ設計やセールスコピー、導線設計まで学べると実案件で活かせます
- 実案件で活かせる「提案力」まで見据えると遠回りしない
まとめ|「全体を知ってから学ぶ」ことが、最大の近道になる

完璧にこの通り進める必要はありません。
でもこの3ステップの全体像を最初に知っておくだけで、情報に振り回されることなく、必要な学びを選んでいけるようになります。
-
ただ作る → 伝わるように作る
-
見せるだけ → 行動してもらえる設計へ
この「学びの順番」がわかっているだけで、あなたの努力は、ちゃんと仕事につながる力に変わっていきます。
\ 私が選んだスクール体験談もあわせてどうぞ /